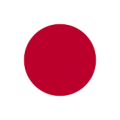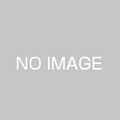幸せになる為には、自覚的に生きている人をより多く知るという事が重要になってきます。
このシリーズでは、そのような自覚的に生きている人たちをご紹介します。
日本では、終末ケアの受け皿になる医療機関が機能していない事の他に、見過ごされている問題があると思います。
それは”死生観”です。
医者というのは、立場上「これ以上の治療は苦痛を増すだけなので、終末ケアに切り替えましょう」という線を引いてはくれません。
延命治療などは、始めたら最後”途中で降りる”のは殆ど不可能です。
でも、特に回復の見込みのない老人の場合は、積極的な治療はかえって体力を消耗させ、延命措置はできても苦痛は取り除けない場合があります。
それでも最後まで可能性を捨てきれず闘病し続け、苦難の末に亡くなる人が圧倒的に多いのです。
もちろん最後まで闘病するのが悪いと言っているのではありません。
それが本当に本人や家族の意思なのか?ということが問題なのです。
それにはまず「自然死とはどういうものなのか?」「人は最後どういう原因で亡くなるのか?」とか「人間らしく穏やかに幕を閉じる方法」をあらかじめ知っておく必要があると思います。
自分は終末期をどう過ごしたいかという事を、家族で話し合っておく事も大切ですよね。
元気なうちに自分の死生観を固めておくのは、今を生きる事とも無縁ではないと思います。
医療の闇にノーを突きつけた女性
今回ご紹介するのは、精神科医のエリザベス・キューブラー・ロスさんです。
世界的にベストセラーになった『死ぬ瞬間』の著者であり、死の間際にある患者の心理や末期患者との接し方を研究した先駆者です。
本に書かれた「死の受容のプロセス」とか「死の受容・5段階」という言葉は、聞いた事がある人も多いかもしれませんね。
彼女がこの道に入るキッカケとなったのは、はじめて医師として医療機関に入った時、病院が死に掛けている患者を扱う態度に衝撃を受けた事です。
死はタブー視され、末期に近づいた患者には機械やチューブに繋がれ、ほとんど人間性を失った存在として冷たく扱われていたのです。
彼女が育ったのはスイスのチューリヒですが、当時はかなり田舎で、まだ近代化されていませんでした。
そこでは死というものは自然な成り行きと捉えられていたし、人が亡くなる時も家族に見守られながら人間らしく最後を迎える事が出来ていたのです。
このギャップにショックを受けたロスさんは、思い切った行動に出ます。
救いたいが故の「暴挙」
ロスさんが病院で始めた事は、当時としてはタブーを破る行為でした。
大学病院へ赴き、終末期の患者に対して、もうすぐ死を迎えるという心境をインタビューして回ったのです。
やはり最初は、病院の猛反対を受けました。
ところが実際にインタビューを試みてみると、当の患者さんたちからは意外にも歓迎されたのです。
彼らは、告知を受けずとも自分がもうすぐ死を迎えるという事を知っていました。
むしろ医師や家族が何も教えてくれない事や、自分に対する扱いに不満を抱えており、ただもう話を聞いて欲しかったのです。
最終的には200人以上の終末期にある患者にインタビューする事になり、ロスさんはその経験から得られた分析を『死ぬ瞬間』にまとめました。
人がその生命の終わりにどんな事を思い、どういう気持でいるのかを追求していく事で、介護者や付き添う人が どのように接したら良いのかという事も見えてきました。
ロスさんの活動は徐々に病院側にも認められる事になり、末期患者へのインタビューは医学生の必須のカリキュラムにまでなったそうです。
そしてこの本が話題を呼びベストセラーとなった事で、こういう問題がある事を人々に認知させた事は、その後のアメリカの医療界を変えるキッカケになったようです。
かつてのアメリカと同じ轍を踏む日本
これは1965年くらいのアメリカでの話です。
でも2019年時点の日本が、まるで当時のアメリカの状況にそっくりというのは、どういう事なのでしょうか。
アメリカでは1970年代後半頃から、終末期を苦痛なく安らかに過ごすための「ホスピスケア」なるものが推進され、今では制度も充実しているようです。
アメリカには「貧富の差」や「健康保険制度の普及」という日本とは別の問題があるので、一概には言えませんが・・・。
最近、私も“自然死”というものについて色々な本を読んでみましたが、日本でも昔は死というものを真摯に受け止め、人間らしい看取りが行われていたそうです。
昔といっても、たぶん昭和の中期くらいまではスイスの例とあまり変わらない状況だったのではないでしょうか。
どうやらアメリカの失敗から学ばず、同じ道を歩んでしまっているようです。